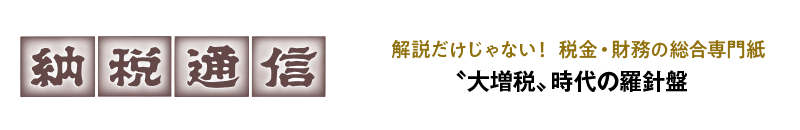

�I�[�i�[�В����������E�Ŗ����V���w�[�ŒʐM�x�B
�o�c�҂݂̂Ȃ炸�A��Ќo�c�̃p�[�g�i�[�ł���ŗ��m�����Ƃ�����M�d�ȏ�Ƃ��đ����̎x���Ă��܂��B���L�҂ɂ�鍑�Ŋ֘A�@�ցA�ŗ��m���ւ̖�����ނŔ|��ꂽ���e�́A��ʎ���o�ρE�r�W�l�X�G���ł͌����ēǂނ��Ƃ͂ł��܂���B
�����T�̒��ڋL���@�@�[��3902���P�ʂ��
�s���Y�̕]�����[�������ρH
�����ő�@�펯�������
�@2026�N�x�Ő������ŁA�s���Y�̑����ŕ]�����[�������{�I�Ɍ��������\�������サ�Ă���B�]���A�u�����ő�͕s���Y��v�Ƃ�����قǁA�s���Y�����p�����ߐł͕x�T�w�ɂƂ��ĕK�{�̐헪���������A���̕]�����[�������������Α����ő�̏펯�͕��ꋎ�邱�ƂɂȂ�B���Y�h�q�헪�̍��{�I�Ȍ������𔗂���Ƃ��������̂��B
�H�������w�����i���d��
�@�߁X�Ɍ��\�����2026�N�x�̗^�}�Ő�������j�ɁA�s���Y�𗘗p���������ő��}�����錩�����荞�ތ������i��ł���ƕ������f�B�A�����B�����𓊎��p�s���Y�ȂǂɊ����đ������邱�Ƃő����Ŋz��}�����@���莋���Ă���Ƃ����B
�@��̓I�Ȍ������̓��e�ɂ��Ă͌����������A���ݕ��サ�Ă���̂́A���s���x�ł͑����ŘH�����ŕ]�����Ă���s���Y���A�w�����̉��i����Ƃ���悤���������e�B�w����̉��i�ϓ��Ȃǂ��������A�Ŋz���Z�o����B�����܂ł������ő�Ƃ��Ă̕s���Y�w�����K������ړI�ł��邽�߁A���������O�T�N�ȓ��ɍw���������ݕ����Ɍ��肷��Ƃ����B�܂��A���z�������ׂ��������ē������i�Ƃ��Ĕ���o���u�s���Y���������i�v�ɂ��Ă��A�]��������������j���B
�@���s�̕]�����@�ł́A�y�n�͘H�����A�����͌Œ莑�Y�ŕ]���z����ɎZ�o�����B�����̕]���z�́A��ʓI�Ɏs��ł̔������i�ł��鎞�������啝�ɒႭ�ݒ肳��Ă���A�s�s���̕s���Y�ł́A�����̔��z�ȉ��ƂȂ邱�Ƃ��������Ȃ��B�Q���~�̌�����s���Y�Ɋ����邾���ŕ]���z���P���~�Ɉ��k����A�����ł�啝�Ɍ��炷���Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B�܂��A�s���Y�����ݕ����������ꍇ�A�݉ƌ��t�n��݉ƂƂ��āA�]���͂���Ɍ��z����A���̓�d�̕]�����������A�u�����ő�͕s���Y��v�Ƃ����펯���x���Ă��������������킯���B
�@�������A���������s��ł̔������i�Ƒ����ŕ]���z�̂������𗘗p���������ő��Ƃ����P�[�X���A�ߔN�������Ă����B���ɖ��ƂȂ��Ă����̂��A���w�}���V�����̒�w�K�ƍ��w�K�Œ��]�Ȃǂ𗝗R�ɉ��i����������ɂ�������炸�A�����ŕ]���z�����������Ƃ𗘗p����A������u�^���}���ߐŁv���B�����~�ɏ�鑊���ł����ߐŇ����邱�̎�@�́A�����܂ł����@�͈͓̔��̃X�L�[���ł͂�����̂́A���œ��ǂ́u�ېł̌������Ȃ��v�Ɩ�莋���A�۔F���鎖�Ⴊ�����������Ă����B���ǁA2024�N�P������́A�^���}���̕]�����[�����̂��̂���������A���Ă̂悤�ȐߐŌ��ʂ͓����Ȃ��Ȃ��Ă��邪�A����ł��A������s���Y�Ɋ�����|�����͕̂ς���Ă��Ȃ��B����̐Ő������ɂ����錩�����́A���̃^���}���ߐł̋K���̖Ԃ��A�����p�s���Y�S�̂ɍL������̂Ƃ����Ă������낤�B
�@����̃��[���ύX�����������ꍇ�A�[�Ŏ҂����ʂ�����͐[�����E�E�E�i���̐�͎��ʂŁc�j
�����ڃR���e���c
 �ŗ��m�V��
�ŗ��m�V��
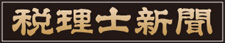
 �В��̃~�J�^
�В��̃~�J�^

 �I�[�i�[�Y���C�t
�I�[�i�[�Y���C�t

�@
