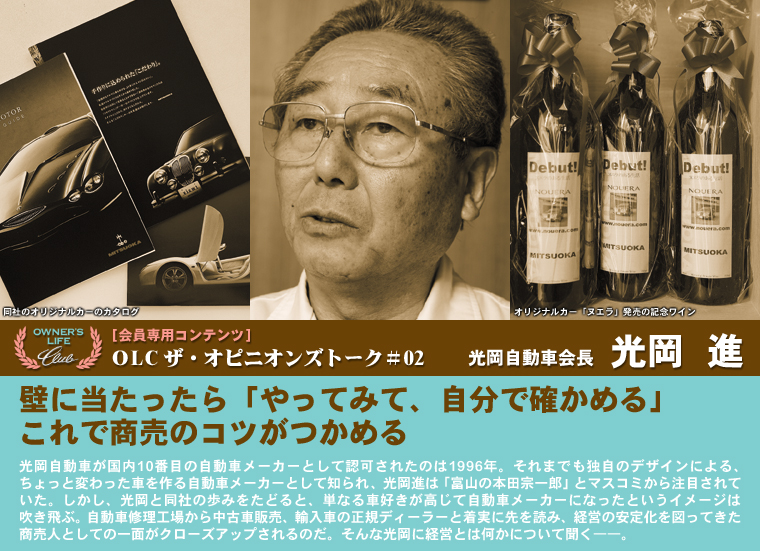
Photo:H.Hamaguchi
自動車メーカーを作るなんて、大それた相談は想定外だった旧運輸省
光岡自動車が日本で10番目となる自動車メーカーとして名乗りを上げたのは94年のこと。 ホンダ以来、33年ぶりとなる快挙ではあったが、自動車メーカーとしての認可には 霞が関の強大な壁が立ちはだかっていた。初の自社オリジナルカーとなった50ccエンジンを積んだゼロハンカー(マイクロカー)・BUBUシリーズの挫折から約10年、 記念すべき自動車メーカーとしての第1号車・ゼロワンの誕生までには、光岡進と霞が関との筆舌に尽くし難い戦いがあった。
当時はこんな小さな会社がメーカーになれるとは、正直、思ってなかったですね。 それまでは改造車をやっていたわけですが、やはりオリジナルなデザインでやろうとすると、 自分たちでフレームを作らないといけないわけです。ただ、日産のシルビアをベースにした ラ・セードを作ったとき、初めてシャーシの長さを伸ばしたんですが、これがあっさりと車検をパスしましてね、 これなら自分たちのフレームにも許可が下りるんじゃないか、という予感のようなものはありました。
これがメーカーになろうと考えた最初のきっかけで、その後、角パイプをハシゴ状に組み合わせたオリジナルフレームの試作を進める一方、 運輸省(当時)に出向いて「自分たちのフレームを許可してほしい」と相談したんです。しかし、担当者はポカンとしてましてね(笑)。 「光岡さん、何をいっておられるの」という感じで、要するにオリジナルフレームに新たな許可を出す、 つまり自動車メーカーを新規に設立する、などという大それた相談なんぞが来るはずはないという感じだったんです。
その後、何度か足を運ぶうちに「これは真剣だな」ということだけは分かってもらえたんですが、 担当者からは「大手のメーカーでさえ赤字なんですから、光岡さん、やめておいた方がいいですよ」と忠告される始末で。 「あんた、会社潰す気か」と(笑)。それでもしつこく食い下がると、 今度は会社の規模だとか生産体制だとか販売体制だとかを書いた書類を提出しなさいといわれましてね。 わけの分からない会社にメーカーの許可を出して国の責任を問われでもしたら大変、ということでの一種の信用調査だったわけです。
あっちにもあるこっちにもある、日本の許認可制度
ところが、あとになって分かったんですが、日本には自動車メーカーの許可を出す際の明確な基準というものがないんですね。 つまり「誰もが許可を取れそうで、実際には誰もが許可を取れない」という仕組みになっていたんです(笑)。 銀行や放送局などの許認可事業も同じで、本来は誰にでも会社を作る権利があるはずなんですけれど、 実際には何だかんだといって許可を出してはもらえないんですね。欧米などでは少量生産の自動車メーカーにも門戸が開かれているんですが、 日本の場合はそうはなっていないのです。
それでもメゲずに食い下がっていたら、今度は運輸省の担当者からウチの検査担当に電話がかかってきましてね。 「あなたからオヤジさんになんとかあきらめるようにいってくれないか」と(笑)。 そのあとも何だかんだとはぐらかされていたんですが、 最後は「光岡さん、メーカーになるんだったら自動車工業会に入ってもらわないと困ります」といわれましてね。 すぐに自動車工業会に飛んでいったんですが、専務理事が「10人くらいは社員を派遣してもらうことになりますが、 光岡さんの会社の規模ではムリなんじゃないですか」と一言。たしかにムリでした(笑)。
で、さらに運輸省に取って返し、「自動車工業会に入らなければメーカーになれないなんて 自動車六法のどこに書いてあるんですか」と迫りましてね。担当者は弱った顔をして、 「もう2週間、待ってくれ」といわれたのです。
そこで2週間たってから再び出向くと、「そんな簡単に許可は出せないし受け付けることも
できない」と。そのあともいろいろなやりとりを繰り返し、担当者もようやくといいますか、
しょうがないという感じでついに重い腰を上げてくれましてね(笑)。
それからですよ、マトモな話が始まったのは。
82年にマイクロカーを作ったときも、そのあとに運転免許制度を変えられてしまい、 それまで原付免許で運転できたものが普通免許でなければ乗れなくなってしまったんです。 あのときも警察庁とずいぶんやり合ったんですが、日本の許認可制度の壁というのは本当に厚かったですね。